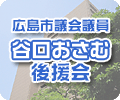2011年9月
稲むらの火(地震の神様)
先日書きました「稲むらの日」を教科書に採用させたのは「今村明恒」という東大の地震学者だそうです。この話を文部省に持ち込んだときは、無下に断られました。「そんなスペースはない」と。今村は発奮し、文部大臣が同席したある会場で講演をすることになり、「ドリアン(臭すぎる果物)の話を載せる余地があって、幼い小国民に地震のことを教える余地が無いものか!」と声高に主張しました。思わず納得した文部大臣は、一転して教科書への掲載を許可したそうです。。
そんなこんなで、今村は「地震の神様」とまで世間に賞賛されるようになりました。「今村明恒」氏について次のような記事がありました。
関東大震災前、今村は関東地方で起こるであろう「大地震」を警告していた。
彼は、日本書紀から始まる「日本の地震の記録」をつぶさに調べ上げ、およそ2,000を超える過去の地震に関して、ソラで唱えられるほどに精通していた。詳細な検証の結果判ったことは、「関東では100年に一度、大地震が起こっている」ということだった。
今村はその研究論文を発表する。「50年以内に東京を大地震が襲う危険性がある。防災対策を徹底すべし。」この論文が発表されたのは1905年、関東大震災の起こる18年前の話である。
ところが、時の新聞社は、「大地震の恐怖」を煽(あお)るような報道をする。パニックに陥った民衆は、ちょっとした地震で家財道具一式を持って逃げ出したりと社会的な大混乱へと発展する。
事態を鎮静化しようと、時の地震学の権威「大森房吉」は、「東京に大地震はない」と断言する。それ以降、今村は「天下のホラ吹き男」となってしまったのである。「私利をはかるために浮説を流布している」とまで世間からは蔑まれた。
今村が主張したかったのは「防災対策」である。しかし、奇をてらいたがるメディアは、「大地震の恐怖」だけしか報道しなかったのである。
その後、歴史は容赦なく関東地方を襲い、史上空前の大被害をもたらした。今村が懸念したように、耐震性の弱い家屋はもろくも「倒壊」。火の元の始末をせずに避難した結果は「大火災」。東京の家屋の7割が消失したと言われる。
「紅蓮の吐き出す煙は、入道雲のごとく渦巻きかえる(今村の日記)」
もし、今村が論文で主張した「家屋の補強(筋交い)」や「火元の注意」などの防災対策がなされていれば……。
今村は激しい後悔の念にかられる。「私の意見が世人のいるるところとならなかったのは、全く自分の研究の未熟と自信の薄かったことによる」
「思えば…思えば…、実に残念で堪(たま)らぬ!」
自らの不明を贖罪すべく、今村は立ち上がった。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ……、考えられるあらゆる手段すべてを使って、「防災への啓蒙活動」を開始する。子どもたちにも伝えねばと、いかに分かりやすく説明するかを工夫した結果、子ども雑誌にはなくてはならぬ「地震のおじさん」と親しまれた。
その一つが冒頭の教科書に載って下りです。
地震の神様・今村明恒は、1870年、鹿児島県鹿児島市に薩摩藩士・今村明清の三男として生まれた。
地震の神様・今村明恒の「今村明恒」は「いまむら あきつね」と読む。
地震の神様・今村明恒の研究分野は、地震学である。
地震の神様・今村明恒の研究機関は、東京帝国大学(現:東京大学)
地震の神様・今村明恒の母校は、東京帝国大学である。
地震の神様・今村明恒は、鹿児島高等中学造士館予科を経て第一高等中学校を卒業後、1891年に東京帝国大学理科大学(現・東京大学)物理学科に進学、大学院では地震学講座に入り、そのまま講座助教授となる。1896年からは陸軍教授を兼任し、陸地測量部で数学を教えた。1899年に、津波は海底の地殻変動を原因とする説を提唱した。現在では広く受け入れられている説であるが、発表当時はほとんど受け入れられなかった。
地震の神様・今村明恒は、震災予防調査会のまとめた過去の地震の記録から、関東地方では周期的に大地震が起こるものと予想し、1905年に、今後50年以内に東京での大地震が発生することを警告し、震災対策を迫る記事「市街地に於る地震の生命及財産に對する損害を輕減する簡法」を、雑誌『太陽』に寄稿した。この記事は新聞にセンセーショナルに取り上げられて社会問題になってしまった。そして上司であった大森房吉らから世情を動揺させる浮説として攻撃され、「ホラ吹きの今村」と中傷された。しかし1923年に関東大震災が発生し、明恒の警告が現実のものとなった。その後関東大震災の地震の予知の研究した功労者として「地震の神様」と称えるようになった。
地震の神様・今村明恒は、1911年に今村式強震計を開発した。
地震の神様・今村明恒は、1923年に亡くなった大森の後を継いで地震学講座の教授に昇進する。1925年に但馬地震、1927年に北丹後地震が発生し、次の大地震は南海地震と考えた明恒は、これを監視するために1928年に南海地動研究所(現・東京大学地震研究所和歌山地震観測所)を私費で設立した。明恒の予想通り1944年に東南海地震、1946年に南海地震が発生した。東南海地震後には南海地震の発生を警告したものの、被害が軽減できなかったことを悔やんだと言われる。
地震の神様・今村明恒は、1929年、1892年に解散していた日本地震学会を再設立し、その会長となった。専門誌『地震』の編集にも携わった。1931年に東大を定年退官したが、その後も私財を投じて地震の研究を続けた。1933年に三陸沖地震が発生した際には、その復興の際に津波被害を防ぐための住民の高所移転を提案した。また、津波被害を防ぐには小学校時代からの教育が重要と考えて『稲むらの火』の国定教科書への収載を訴えた。それが実現した後、1940年に『『稲むらの火』の教え方について』を著して、その教え方についても詳しく指導している。
地震の神様・今村明恒は、1944年に東南海地震が発生した際には、掛川-御前崎の水準測量を行なっていた。この時、地震前日から御前崎が隆起する動きが確認できた。これが現在の東海地震の発生直前の地震予知が可能であるという根拠とされている。
(地震の神様・今村明恒についてのデータは、「今村明恒 - Wikipedia」より、引用・編集して掲載しています。)
重陽の節句
今日(9月9日)は、重陽の節句です。
重陽の節句(ちょうようのせっく)
五節供の1つで、9月9日を指します。旧暦ではキクが咲く季節であることから「菊の節句」とも呼ばれています。
元々は支那の考え方で、「九」との陽数(奇数)の中で一番大きな数が重なることから「重陽」と呼び、めでたい日とされてきた。起源は六朝時代の桓景(かんけい)の故事にちなんでおり、この日に高いところに登り、菊酒を飲めば災いが避けられるとして、9月9日になると人々は酒肴や茶菓などを持って小高い山に登り、紅葉を眺めながら1日を楽しみ、邪気を払ったといわれている。古来支那でキクの花は不老長寿に結びつくと信じられており、重陽には特にキクの花を浮かべた菊酒を飲むのが慣わしになっていた。
この習わしが飛鳥時代に日本に伝わり、宮廷行事として菊花宴が開かれるようになり、平安時代には重陽節として正式な儀式となった。『紫式部日記』には、8日の夜に綿をキクの花にかぶせ、翌朝、露にぬれたキクの香りのする綿で肌をぬぐうと長寿を保つことができるとの「菊綿(きくわた)」や「菊被綿(きくののせわた)」と呼ばれる習慣が描かれている。
江戸時代になると、重陽の節句は五節供の1つ「菊の節供」として民間にも広まっていった。旧暦の9月9日は現在の10月頃にあたり、これは田畑で収穫が行われる時期に当るため、農山村などでは「栗の節句」とも呼ばれて栗ご飯などで節句を祝ったといわれる。明治時代以降、この風習は他の節句に比べて少しずつ薄れていくが、現在でもこの日に、キクにちなんで各地でキクの品評会が開かれている。
旧暦の9月9日というと現在では10月になりますから、ちょうど田畑の収穫も行われる頃で、農山村や庶民の間では栗の節句とも呼ばれて栗ご飯などで節句を祝ったということです。
さかんに行われていた重陽の節句が、現代に引き継がれていないのは、旧暦から新暦にこよみが移り、まだ菊が盛んに咲く時期ではなくなってしまったことが大きいのかもしれません
節句(せっく)
伝統的な年中行事を行う季節の節目となる日のこと。「節供(せっく)」とも。古くは「節日(せちにち)」と呼ばれ、節日には朝廷において節会と呼ばれる宴会が開かれた。古代支那から伝わった暦上の風習を指し、日本の生活に合わせてアレンジされていくつもの節日が伝わっていたが、そのうちの5つを江戸時代に幕府が公的な行事・祝日として定めたのが節供である。
五節句
・人日(じんじつ)
1月7日:七草
・上巳(じょうし/じょうみ)
3月3日:桃の節句
・端午(たんご)
5月5日:菖蒲の節句
・七夕(しちせき/たなばた)
7月7日:たなばた
・重陽(ちょうよう)
9月9日:菊の節句
(インターネット記事引用)
稲むらの火
昨日(9月7日)NHK『スタジオパークからこんにちは』で「稲むらの火」の話が紹介された、再放送が有りました。
「稲むらの火」とは、Lafcadio Hearn (1890ー1940,、日本帰化名、小泉八雲)の著作に見られます。後に、それを中井常蔵氏(1907ー1994)が「稲むらの火」という短編に仕立て直しました。この「稲むらの火」は戦前から戦後にかけて(1937ー1947)、小学校の国語の教科書に使われ、今では、津波防災教育の優れた教材として知られています。
小学校では、平成23年4月から、新学習指導要領が全面実施となりました。指導要領の改訂に伴い、教科書の内容も大きく変わっています。
教科書はいくつかの出版社から出ていて、どの教科書を使うか管轄の教育委員会が採択します。よって、地域によって使う教科書が違っていたりします。
(どの教科書を使っても、学習指導要領で定められた内容が網羅できるように作られています。)
新しい国語の教科書(光村図書出版)に『稲むらの火』という作品がありました。(64年ぶりに採用されました)掲載は 大震災の発生前に決まっていたそうです。もっと早くから掲載していたら「釜石の奇跡」のような事例が沢山出て来ていたかもしれません。
小泉八雲の名作、「生ける神」をもとにして、教科書用テキストとして作られたのが、この名作「稲むらの火」である。子供達にとって、やや難しい表現が見られるものの、五兵衛 つまり浜口梧陵の崇高な生き方を教えている教科書用テキストです。
教科書 原文
「これはただ事ではない。」
とつぶやきながら五兵衛は家から出てきた。今の地震は別に烈(はげ)しいという程のものではなかった。しかし長いゆったりとしたゆれ方と、うなるような地鳴りとは、老いた五兵衛に、今まで経験したことのない不気味なものであった。五兵衛は、自分の庭から、心配げに下の村を見下ろした。村では、豊年を祝うよい祭りの支度に心を取られて、さっきの地震には一向気がつかないもののようである。
村から海へ移した五兵衛の目は、忽(たちま)ちそこに吸い付けられてしまった。風とは反対に波が沖へ沖へと動いて、見る見る海岸には、広い砂原や黒い岩底が現れて来た。
「大変だ、津波がやって来るに違いない。」と、五兵衛は思った。このままにしておいたら四百の命が、村もろ共一のみにやられてしまう。もう一刻も猶予(ゆうよ)はできない。
「よし。」
と叫んで、家にかけ込んだ五兵衛は、大きな松明(たいまつ)を以て飛び出してきた。そこには取り入れるばかりになっているたくさんの稲束が積んである。
「もったいないが、これで村中の命が救えるのだ。」と五兵衛は、いきなりその稲むらの一つに火を移した。風にあふられて、火の手がぱっと上がった。一つ又一つ、五兵衛は夢中で走った。こうして自分の田のすべての稲むらに火をつけてしまうと、松明を捨てた。まるで失神したように、彼はそこに突っ立ったまま、沖の方を眺めていた。
日はすでに没して、あたりがだんだん薄暗くなってきた。稲むらの火は天をこがした。山寺では、此の火を見て早鐘をつき出した。
「火事だ。庄屋さんの家だ。」と村の若い者は、急いで山手へかけ出した。続いて、老人も、女も、子供も、若者の後を追うようにかけ出した。
高台から見下ろしている五兵衛の目には、それが蟻(あり)の歩みのように、もどかしく思われた。やっと20人ほどの若者がかけ上って来た。彼らはすぐ火を消しにかかろうとする。五兵衛は大声に言った。
「うっちゃっておけ。?大変だ。村中の人に来てもらうんだ。」
村中の人は追々集まってきた。五兵衛は、後から後から上ってくる老幼男女を一人一人数えた。集まって来た人々は、燃えている稲むらと五兵衛の顔とを代る代る見くらべた。
その時、五兵衛は力一杯の声で叫んだ。
「見ろ。やって来たぞ。」
たそがれの薄明かりをすかして、五兵衛の指さす方を一同は見た。遠く海の端に、細い、暗い、一筋の線が見えた。その線は見る見る太くなった。広くなった。非常な早さで押し寄せて来た。
「津波だ。」
と、誰かが叫んだ。海水が絶壁(ぜっぺき)のように目の前に迫ったと思うと、山がのしかかってきたような重さと、百雷の一時に落ちたようなとどろきとを以て、陸にぶつかった。人々は我を忘れて後ろへ飛びのいた。雲のように山手へ突進して来た水煙の外は、一時何も見えなかった。
人々は、自分等の村の上を荒れ狂って通る白い恐ろしい海を見た。2度3度、村の上を海は進み又退いた。
高台では、しばらく何の話し声もなかった。一同は波にえぐり取られてあとかたもなくなった村を、ただあきれて見下ろしていた。
稲むらの火は、風にあふられて又もえ上がり、夕やみに包まれたあたりを明るくした。始めて我にかえった村人は、此の火によって救われたのだと気がつくと、無言のまま五兵衛の前にひざまづいてしまった。
(インターネット「稲むらの火」転載)