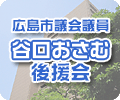ピンクリボン 2009:11:19:06:25:44
昨年、一昨年とカープ・サンフレッチェの試合にピンクリボン運動を行ないたいという申し出があり、市役所の職員さんと一緒に参加しました。現在も続いていますピンクリボン運動ですが、一昨日、公明党の政治パーティーに行くと、東広島市の市長さんがスーツの胸に付けておられました。
ピンクリボン運動
ピンクリボン運動とは乳がんの「早期発見・早期診断・早期治療」の大切さを世界の女性たちに伝える運動です。
胸元にピンク色のリボンをつけることでセルフチェックや定期検診をうながし、乳がんに対する意識を高めるのが目的です。
ピンクリボン運動の歴史
ピンクリボン運動は1980年代にアメリカで始まりました。乳がんで若くして亡くなった女性の母親が、残された家族と一緒にピンクリボンを作ったのが最初と言われています。
「乳がんで命を落とさないように」という女性たちへのメッセージと「同じ悲劇を繰り返したくない」という母の思いが込められています。
当時のアメリカでは乳がんにかかる女性は8人に1人と多く、死亡率も高かったそうです。
一方、日本でピンクリボン運動が広まったのは2000年代に入ってからのことです。街を歩いて乳がんを啓蒙するウォーキングや、ピンク色にライトアップされた東京タワーやレインボーブリッジなどが人々の注目を集めました。
20人に1人。日本人女性が乳がんにかかる割合は驚くほど高い食生活の欧米化、出産の高齢化などにともない、乳がん患者は急増しています。
1996年には乳がんが日本人女性のがん罹患率第1位になりました。
年間約40,000人の女性が乳がんを患うとされ(約20人に1人の割合)、死亡数も年々増えています。
90%の人が10年生存。早期に発見できるほど完治も望める乳がんは早期発見であるほど治癒率が高い病気です。2センチ以下のしこりで、リンパ節への転移がない状態(?期)であれば約90%の人が10年生存している、つまりほぼ完治しているという結果が出ています。
また、がんが小さいうちに発見できれば女性にとって大切な乳房を温存できます。
女性の30?40代は乳がんにかかるレッドゾーン乳がんにかかる人が多いのは30〜40代の女性。
最もリスクが高まるのは40代後半ですが、20代でも発症が認められています。「まだ若いから」と無関心ではいられません。
乳がんは一般的に次の様な人がなりやすいといわれています。
・初産の年齢が30歳以上の方
・出産経験のない方
・初潮年齢が早かった方(11歳以下)
・閉経年齢が遅かった方(55歳以上)
しかし、出産・授乳経験があっても、閉経後でも乳がんになる場合があります。
年代にかかわらず、乳がんの危険性を認識したいものです。
マンモグラフィーで乳がん検査
年間1万人が命を落とすとされている乳がん。厚生労働省は、40歳以上の女性の乳がん検診は従来の視触診だけではなく、
マンモグラフィー(乳房レントゲン撮影)をするべきという指針をだしました。
マンモグラフィー検査
そもそもラテン語で『マンマ(mamma)』は『乳房』のこと。だから乳房のレントゲン写真をとる検査は『マンモグラフィー(mammagraphy)』となるわけです。
ちなみに一台約3000万円くらいです。マンモグラフィー検査は欧米では一般的な検査で、アメリカではその受診率は28.8%(1987年)から66.9%(1998年)まで増加しています。
(GE横河メディカルシステム調べ)

マンモグラフィー検査の機械
慢性疲労症候群 2009:11:18:08:26:58
J1のサンフレッチェ広島森崎和幸選手が慢性疲労症候群にかかっていましたが復帰しました。
2009年6月サンフレッチェ広島から次の様に公式発表されていました。大変な病気にかかって、復帰には相当時間かかると思われていました。(精神的なうつ病状態になることが多い病気と言われている)
サンフレッチェ広島所属の森崎和幸選手の状況について以下の通り診断されましたので、お知らせします。2006年に発症したオーバートレーニング症候群の再発だと思っていたが、事態はより深刻であるようです。
■診断名:慢性疲労症候群
■備考 :現在のところ復帰時期については未定。回復には十分な休養が必要と診断されました。
(2009年6月16日)
慢性疲労症候群について調べてみました。
慢性疲労症候群(CFS)
極度の疲労(強い消耗感、極端なスタミナ不足)が一日中もしくは一日のほとんどの時間、生じている状態が長期間続く状態のことをいいます。
人間だれでも疲労を感じることはあります。大抵は休養や睡眠をとることで疲労は回復されますが、中にはどんなに休養や睡眠をとっても疲労が回復されない場合があります。
このようにいつも疲労を感じている人は、男性の5人に1人、女性では3人に1人いると言われています。長い労働時間、ストレスなどで、慢性的な疲労を感じる場合がありますが、このような要因が全くないにも関わらず、慢性的な疲労、それも日常生活に支障をきたすほどの極度の疲労を感じる人も少数ながらいるのです。
この場合、慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome)であることが疑われます。
アメリカでは慢性疲労免疫障害症候群(CFIDS)として知られています
慢性疲労症候群(CFS)は、これまで健康に生活していた人に原因不明の強い全身倦怠感、微熱、頭痛、脱力感や、思考力の障害、抑うつ等の精神神経症状などが起こり、この状態が長期にわたって続くため、通常の日常生活が送れなくなるという病態です。
具体的な症状としては、患者によってかなり様々な表れ方をしますが、多くは風邪やインフルエンザの症状と似ています。
◎頭痛、めまい、かすみ目
◎筋肉痛、関節痛、リンパ節痛、凝り
◎不安感、認識力低下、うつ状態
◎睡眠障害、寝汗、
◎胃腸障害、吐き気、食欲不振、下痢
◎咽頭炎、口渇、咳
◎微熱、筋力低下、
症状の重さは、患者により大きく異なります。同じ患者であっても時期によって、軽い疲労のときもあれば、寝たきりで動けない状態にまでなることがあります。またこれらの症状は繰り返され、時期によって現れる症状が異なる場合も多く見られます。
「慢性疲労」と「慢性疲労症候群」は、言葉はよく似ていますが、きちんと区別して考える必要があります。(疲れる原因がある程度わかっていて、疲労感も日常の生活が続けられる程度のものである場合、これは「慢性疲労」と呼ばれます。
ほとんどの場合、十分な休息をとる等、疲労となる原因を取り除けば回復します。ただし、慢性疲労から慢性疲労症候群に移行するケースもありますので、注意が必要です。