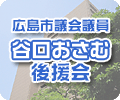駐広島大韓民国総領事 歓迎会 2011:04:16:06:57:59
昨日(4月15日)広島県日韓親善協会主催の「駐広島大韓民国総領事館」「辛享根総領事」の歓迎会が18時30分よりリーガロイヤルホテル広島で有りました。
今回就任された辛享根総領事は、お父上の辛永朱氏が広島で被爆し、その後帰国して韓国原爆被爆者協会を設立、初代会長として在韓被爆者の救援に尽力したことで知られています。「被爆2世の総領事」として話題になっています。
広島県日韓親善協会は 広島(県)と韓国の友好交流を民間レベルですすめようという組織です。広島市議会は日韓親善協会有志の会として22人の議員が参加しています。
広島県と韓国との間は1991年(平成3年)6月に広島-ソウル間の定期航空路線が開設され、その後1994年(平成6年)のアジア大会の開催などもあって交流が活発になりました。
1997年(平成9年)には韓国総領事館が下関から広島に移設され、さらに 2002年(平成14年) 10月には 広島市と釜山広域市を結ぶ初の国際定期フェリーが就航し、広島(県)と韓国の間は 一層 近くなりました。
広島 - 釜山の定期フェリーは船体の老朽化などが敬遠されて利用者が低迷し、現在 休止となっています。駐広島韓国総領事館や広島県は航路の再開を目ざして関係方面へ働きかけをしています。
この間 広島市が大邱広域市と姉妹提携した(1997年)のをはじめ、呉市は鎮海(チネ)市(慶尚南道)と(1999年)、三次市は泗川(サチョン)市と提携(2001年)。福山市と浦項(ポハン)市は1979年から提携して友好関係を築いています。
当協会も広島アジア競技大会が開催された1994年(平成6年)に釜山広域市の韓日親善協会と友好提携したほか、広島市が提携している大邱広域市や、広島県が交流している慶尚南道の韓日親善協会と交流をすすめています。
また 広島県内の民間諸団体が行っている 韓国との交流事業の支援や在広韓国人留学生の支援などにも力を入れています。
このうち、姉妹提携している広島市と大邱広域市については、広島市が制定している「大邱の日」の記念行事を 06年から 5月の広島フラワーフェスティバルの会場を舞台に開催しています。
特に姉妹提携 10周年の 07年には大邱広域市の金範鎰(キムポミル)市長ら代表団を広島市に迎えて、盛大に記念式典を行いました。
また、セレモニーとは別に フラワーフェスティバル会場に「韓国・大邱マダン」というブースを設け、特に大邱広域市を含む 韓国の伝統文化や観光地を紹介、韓国食の販売などを行っています。ブース展開には、広島大学や広島修道大学に学ぶ留学生達も積極的に参加し、チマ・チョゴリの試着コーナーや、ハングルで自分の名前を書くコーナーなどで活躍しています。
韓国をPRするブースは 秋に広島城趾公園で行われるひろしまフードフェスティバルでも開設して人気のブースのひとつになっています。
公館沿革
1966年 5月 駐下関領事館 開館
1980年 5月 総領事館 昇格
1996年12月 駐下関総領事館 閉鎖(移転)
1997年 1月 駐広島総領事館 開設(鉄砲町所在)
2006年12月 駐広島総領事館 移転(袋町所在)
2010年 3月 現庁舎に移転(東荒神町所在)
歴代公館長
公館長 氏名 在 任 期 間
初代 朴匡海 1966年 5月ー1967年10月
2代 韓 杞 1967年10月ー1972年10月
3代 朴種泝 1972年10月ー1975年 4月
4代 鄭燦植 1975年 4月ー1977年 9月
5代 宋升鉉 1977年 9月ー1980年 7月
6代 慮在朝 1980年 7月ー1982年 9月
7代 梁亀燮 1982年10月ー1985年10月
8代 呉士烈 1985年11月ー1987年 5月
9代 金宇相 1987年 5月ー1990年11月
10代 朴文奎 1990年11月ー1994年 7月
11代 白善君 1994年 7月ー1998年 4月
12代 曺圭泰 1998年 4月ー2000年 8月
13代 朴承武 2000年 8月ー2002年 8月
14代 李河鎭 2002年 8月ー2004年 3月
15代 金演権 2004年 3月ー2006年12月
16代 徐榮振 2006年12月ー2008年 5月
17代 許徳行 2008年 5月ー2011年3月
18代 辛亨根 2011年 3月 現在
(広島県日韓親善協会ホームページ引用)
国難 2011:04:15:07:00:58
3月11日の東北関東大震災で、地震・津波・原発事故と三重苦に合っている日本です。戦後最大の国難と言える状況ではないでしょうか。日本国民がこぞってこの国難に立ち向かっていかなければならないと思います。自粛ムードは有りますが、元気な西日本が元気を東日本に送らなければならないと思います。応援ムードを出さなくてはなりません。自粛ムードに流されて個人消費まで落ち込んでは日本の没落につながります。今こそ、西日本では心に痛みを持ちつつ平生通りの消費活動をすることが必要だと思います。「宴会を援会」に変えて頑張りましょう。
共同通信が「フランシス フクヤマ氏」からの手紙を掲載していました。非常に参考になる内容だったので転用しておきます。
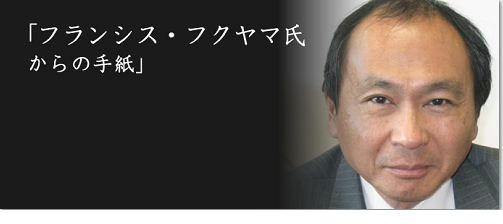
被災者の苦しみに報いよ
著書「歴史の終わり」で知られる日系の米政治学者フランシス・フクヤマさんが、日本は東日本大震災の被害との取り組みを通じ、政治の再生を図れと訴える一文を寄せた。政治再生を実現することこそ、被災者の苦しみに報いる道だという。
新たな政治生まれ出よ 危機通じ国家目標意識を
巨大地震の直後の大津波、さらに福島第1原発での危機的事故。米市民すべてが、恐怖心だけでなく、同情の思いを持って、事態の展開を見守っている。信じられないような破壊の光景だ。被災者らの忍耐強さ、彼らを助ける人々の英雄的行動。信じられないようなニュースが伝えられている。
これから先、さらに遺体が回収されれば、もっと悲しい物語が出てくるだろう。市民のためにとてつもない献身的犠牲を払う人々の物語も生まれるだろう。特に原発でそうしたことが起きそうな気がする。
大変な状況なのにもかかわらず、日本人は気高い精神を持ち、実に冷静にこの悲劇に立ち向かっている。こんな風に悲劇を受け止めることのできる社会は他にないだろうと思う。
今回の大地震と津波は自然の猛威を思い起こさせただけでない。先進技術社会がいかに複雑なシステムに頼っているかも教えてくれた。携帯電話やインターネットだけでなく、電気や水など基本的なものが使えなくなると、人はいかに無力になるかも分かった。
日本人がすさまじいまでの苦しみ、心の痛手を負うのは初めてではない。1923年の関東大震災や第2次世界大戦での敗戦の時も、同様であった。しかし、ある意味で、日本人はつまずいたり、苦難に出会ったりした時にこそ、最高の資質を発揮してきた。国家再生のためにいかにして結束するかを理解し、「共通善」に向かって喜んで自己犠牲の精神で取り組んできた。
今回の国家的悲劇が新たな日本政治の契機となることを、私は期待する。近年の日本は、ライバル相手に目先の得点稼ぎばかりに専念する政治家たちの内輪争いに困らされてきた。政治家たちは真剣に力を合わせ、深刻な長期的な課題を解決しようとしてこなかった。そうした点では、米国の政治家と行動が似通っていた。米国の政治家も党派対立ばかりで、国家の長期的問題への取り組みをおろそかにしてきた。
日本は人口減と高齢化、それにともなう経済・財政課題の全てに直面する最初の先進国家である。日本に必要で欠けているのは、つまらない抗争などにかまけず、国家経済の長期的な健全化を図るために必要な自己犠牲へと国民を引っ張っていける政治指導だ。
いつも通りやっていればなんとかなるという慢心から人を目覚めさせるには、時として厳しい精神的苦痛が必要となる。それが人間の性だというのは残念ながら事実である。大津波被害への短期的な取り組みで人々の粘り強さが試される。そこを通じ、しっかりとした国家目標意識が生まれ、その意識が当面の危機を越えて続いていくことになるかもしれない。そうなれば、この大災害の被災者らの苦しみも、いくぶんかは報われることになろう。
(共同通信)インターネット記事転用